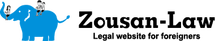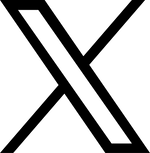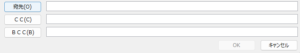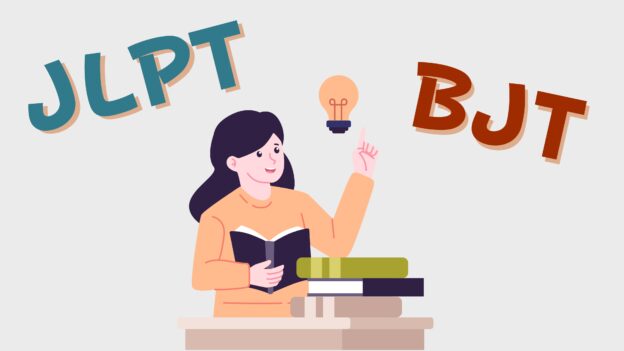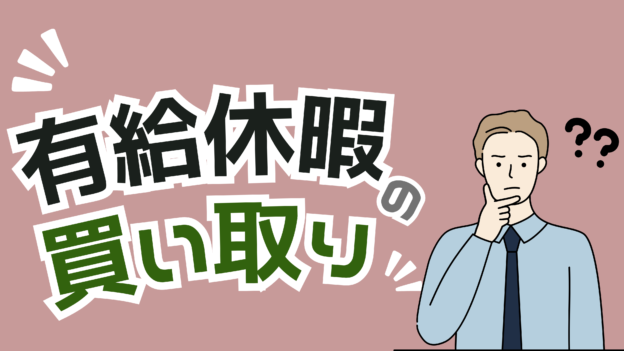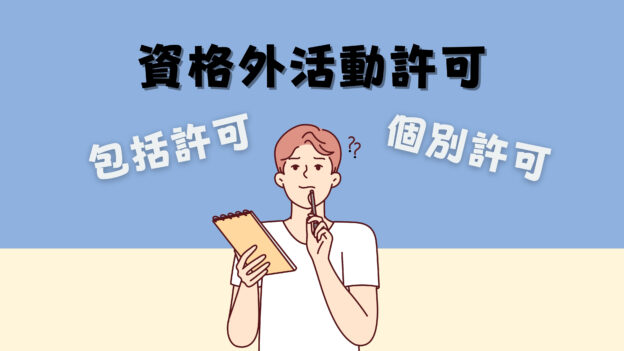日本語を母語としない方々が日本語能力を証明する際、主に「日本語能力試験(JLPT)」と「ビジネス日本語能力テスト(BJT)」の二つの試験が利用されています。これらの試験は目的や評価基準が異なり、それぞれ独自の特徴を持っています。以下、両試験の概要と相違点について詳しく説明します。
1. 試験の目的と対象
◆日本語能力試験(JLPT):日常生活や一般的な場面での日本語能力を測定することを目的としています。N5(最も易しい)からN1(最も難しい)までの5段階にレベル分けされており、自分のレベルに合った試験を選択して受験します。
◆ビジネス日本語能力テスト(BJT):ビジネスシーンに特化した日本語のコミュニケーション能力を評価する試験です。ビジネス特有の言葉遣いやコミュニケーション能力を測定し、日本語を母語としないビジネス関係者や学生を対象としています。
2. 試験内容と評価方法
◆JLPT:「言語知識(文字・語彙・文法)」「読解」「聴解」の3つのセクションで構成されています。各セクションの得点に基づき、合否が判定されます。
◆BJT:「聴解」「聴読解」「読解」の3部門で構成され、ビジネス場面を想定した問題が出題されます。合否の判定はなく、0点から800点までのスコアと、J1+からJ5までの6段階のレベルで評価されます。
3. 試験の実施方法と頻度
◆JLPT:年に2回(7月と12月)実施され、試験日は全世界で統一されています。試験はペーパーベースで行われます。
◆BJT:コンピュータを使用したCBT(Computer Based Testing)方式で実施され、年間を通じて複数回受験が可能です。受験者は希望する日時と会場を選択できます。
※再受験の場合、前回の試験から3ヵ月以上の間隔を空ける必要があります。

4. 受験料
◆JLPT:日本国内での受験料は税込7,500円です。
◆BJT:日本国内での受験料は税込7,000円です。
※2024年12月現在の情報。海外での受験料は受験地によって異なります。
5. 受験のメリット
◆JLPT:日本国内外での就職や進学の際、日本語能力の証明として広く認知されています。
◆BJT:ビジネスにおける日本語運用能力を評価するため、特にビジネスシーンでの日本語力を必要とする職種で有利です。また、JLPTと同様で、BJTのスコアは法務省の入国管理局で日本語能力の証明書類として提出することができ、高度人材ポイント制での加点対象にもなります。
6. 試験結果の活用
◆JLPT:合否判定が行われ、合格者には認定証が発行されます。結果は主に進学や就職時の日本語能力の証明として使用されます。
◆BJT:スコアとレベルで評価され、合否の概念はありません。結果はビジネスシーンでの日本語コミュニケーション能力の指標として活用されます。
JLPTは日常生活や一般的な場面での日本語能力を測定する試験であり、BJTはビジネスシーンに特化した日本語のコミュニケーション能力を評価する試験です。
目的や利用シーンに応じて、適切な試験を選択することが重要です。特にビジネスの場で日本語を使用する予定がある場合、BJTの受験を検討することをおすすめします。