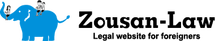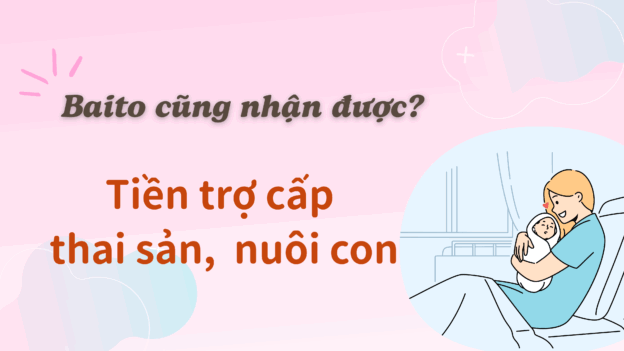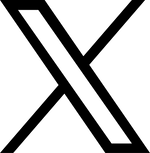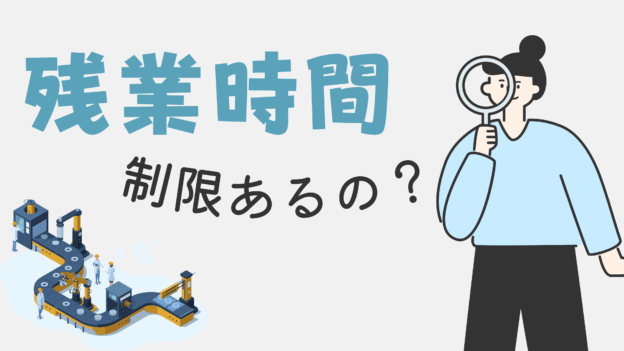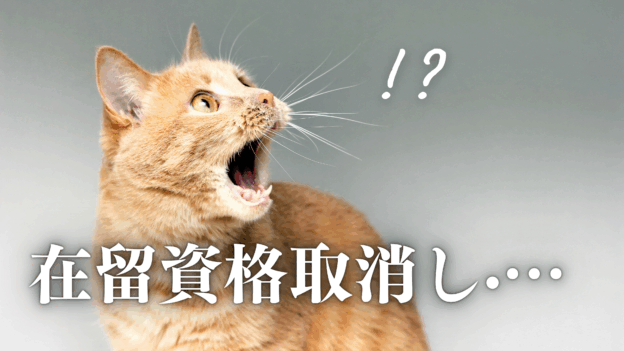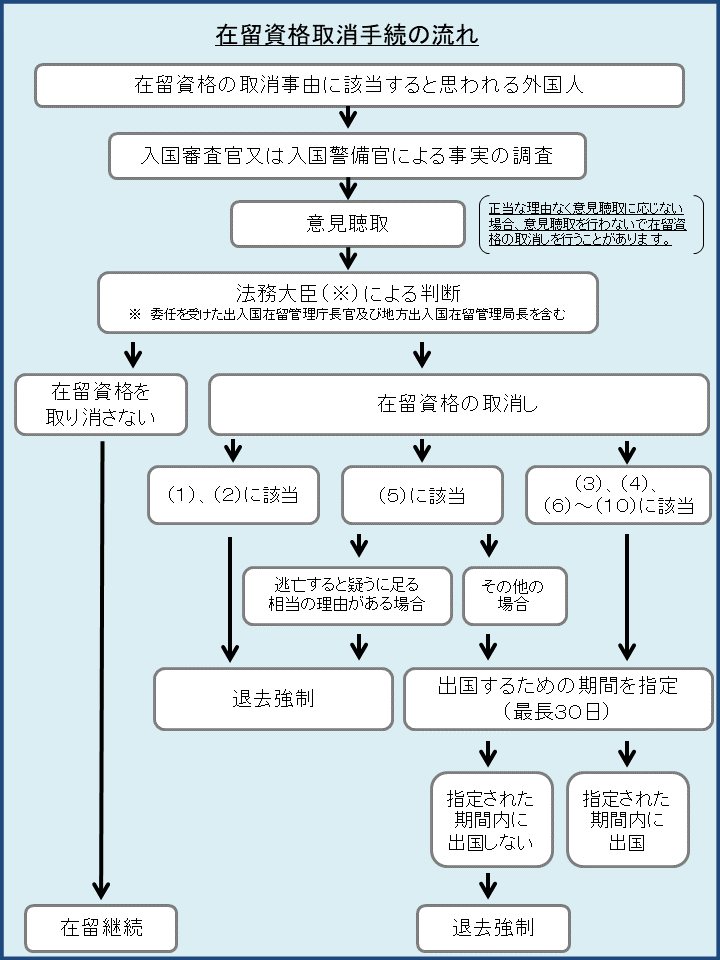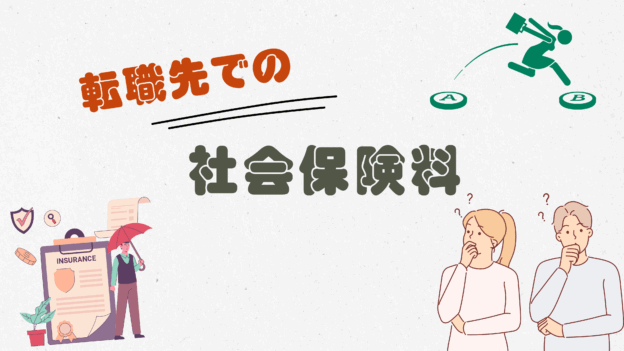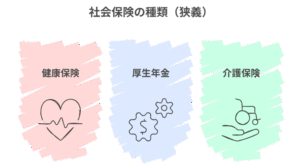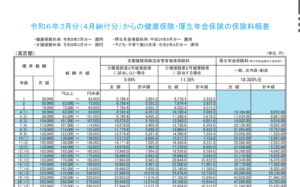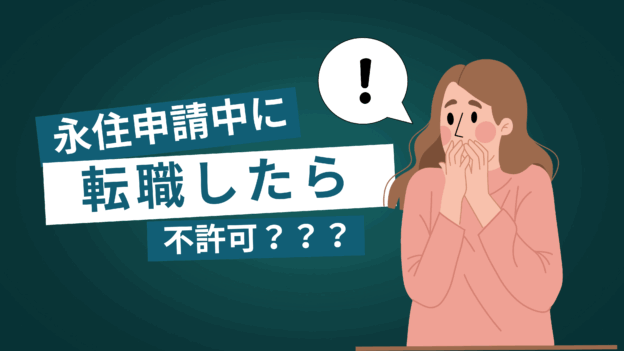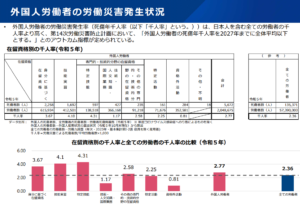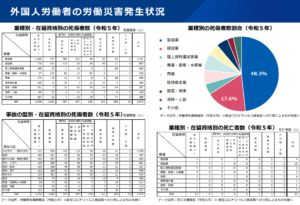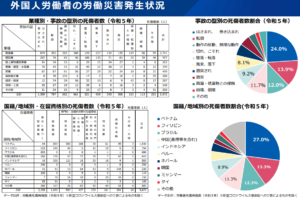制度の概要
在留資格の取消しとは、本邦に在留する外国人が、偽りその他不正の手段により上陸許可の証印等を受けた場合や、在留資格に基づく本来の活動を一定期間行わないで在留していた場合などに、当該外国人の在留資格を取り消す制度です。
在留資格が取り消される主な原因は、以下の3つの類型に大別できます。
➊ 不正な手段による在留資格・上陸許可の取得
虚偽の書類提出や虚偽申告を行うなど、不正な手段を用いて在留資格や上陸許可を得た場合に該当します。
❷ 在留資格に基づく活動の不履行または逸脱
許可された在留資格に応じた活動を、正当な理由なく一定期間(例えば、就労系の在留資格では3か月以上、配偶者等の身分系の在留資格では6か月以上)継続して行わない場合などがこれに当たります。
❸ 居住地に関する届出義務の違反
具体的には、中長期在留者が90日以上居住地の届出を怠った場合や、虚偽の住所を届け出た場合などが挙げられます。
具体的に、在留資格を取り消す場合は、入管法の第22条の4第1項に規定されており、法務大臣は、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、外国人が現に有する在留資格を取り消すことができます。
(1) 偽りその他不正の手段により、上陸拒否事由該当性に関する入国審査官の判断を誤らせて上陸許可の証印等を受けた場合。
(2)(1)のほか、偽りその他不正の手段により、本邦で行おうとする活動を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合(例えば、本邦で単純労働を行おうとする者が「技術」の在留資格に該当する活動を行う旨申告した場合) 又は本邦で行おうとする活動以外の事実を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合(例えば、申請人が自身の経歴を偽った場合)。
(3)(1)又は(2)に該当する以外の場合で、虚偽の書類を提出して上陸許可の証印等を受けた場合。本号においては、偽りその他不正の手段によることは要件となっておらず、申請人に故意があることは要しません。
(4) 偽りその他不正の手段により、在留特別許可を受けた場合。
(5) 入管法別表第1の上欄の在留資格(注)をもって在留する者が、当該在留資格に係る活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留している場合(ただし、正当な理由がある場合を除きます。)。
(6) 入管法別表第1の上欄の在留資格(注)をもって在留する者が、当該在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合(ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除きます。)。
(7) 「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留する者(日本人の子及び特別養子を除く。)又は「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留する者(永住者等の子を除く。)が、その配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合(ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除きます。)。
(8) 上陸の許可又は在留資格の変更許可等により、新たに中長期在留者となった者が、当該許可を受けてから90日以内に、出入国在留管理庁長官に住居地の届出をしない場合(ただし、届出をしないことにつき正当な理由ある場合を除きます。)。
(9) 中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に届け出た住居地から退去した日から90日以内に、出入国在留管理庁長官に新しい住居地の届出をしない場合(ただし、届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除きます。)。
(10) 中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に虚偽の住居地を届け出た場合。
在留資格の取消しをしようとする場合には、入国審査官が、在留資格の取消しの対象となる外国人から意見を聴取することとされており、当該外国人は、意見の聴取に当たって意見を述べ、証拠を提出し、又は資料の閲覧を求めることができます。
(3ヶ月以上仕事を休んだからといって、自動的に在留資格が取り消されるわけではありません!)
在留資格が取り消されることとなった場合であって、上記2の(1)又は(2)に該当するときは、直ちに退去強制の対象となります。
一方で、上記2の(3)から(10)までに該当するときは、30日を上限として出国のために必要な期間が指定され、当該期間内に自主的に出国することになります。
ただし、上記2の(5)に該当する場合のうち、当該外国人が逃亡すると疑うに足る相当の理由がある場合は、直ちに退去強制の対象となります。
指定された期間内に出国しなかった場合は、退去強制の対象となるほか、刑事罰の対象となります。
(注)入管法別表第1の上欄の在留資格
「外交」、「公用」、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」、「特定技能」、「技能実習」、「文化活動」、「短期滞在」、「留学」、「研修」、「家族滞在」、「特定活動」
在留資格取消手続の流れ
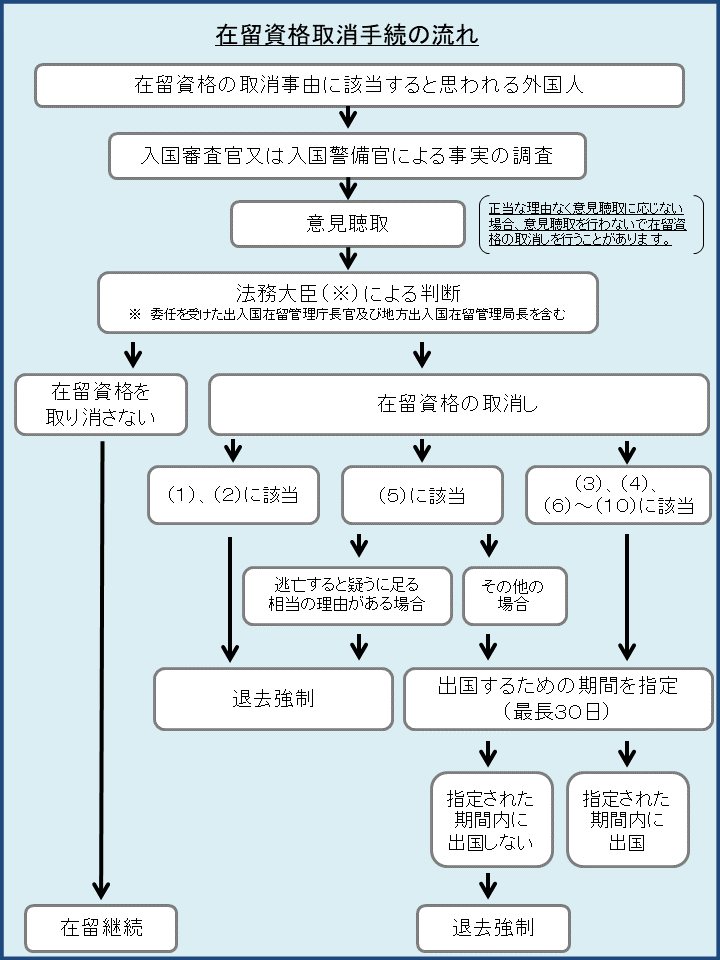
※出入国在留管理庁のホームページより